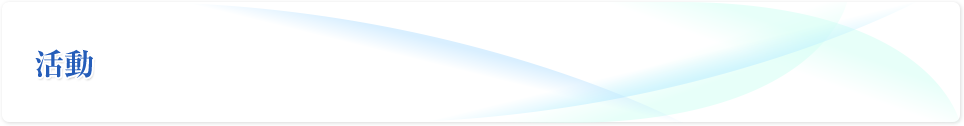活動方針
岩手県小学校長会は、昭和38年結成以来、本県小学校教育の振興発展に寄与すべく、絶えず真摯な研鑽と実践を重ねるとともに、会の総力を挙げて教育諸条件の整備に努めてきた。この半世紀以上にわたる間、幾多の困難に直面しながらも、その課題解決に主体的に取り組み、多くの成果を上げ今日に至っている。
現在、我が国は、不安定な世界情勢の中、情報化や少子高齢化等、社会の急激な変化に伴う高度化・複雑化した諸課題に直面し、加えて、感染症や気候変動、自然災害等への対応も迫られ、多くの課題を抱えている。
このような中、学校教育には一人一人の児童が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるよう、その資質や能力を育成することが求められている。
そのために学校は、学校の役割を再認識し、子どもの学びの保障と多様な幸せとともに、日本社会に根ざしたウェルビーイングの向上を目指し、一人一人の可能性を最大限に引き出す教育の推進に取り組む必要がある。同時に、変化に対応するという発想から、「変化の中で自ら新たな価値を創り出す」という発想に転換し、学校における働き方改革の推進、教員不足の問題、心身に不調を抱える教員の増加、特別な支援を要する児童への対応、不登校やいじめへの対応等、顕在化してきた多くの教育課題に向き合うことが重要である。また「いわての復興教育」においては、震災や復興教育に関する教職員の世代間の認識の差や意識の低下、さぽーとを必要としている児童の増加や地域社会のコミュニティの弱体化等の課題があることから、復興教育に課された意義を再認識し、継承すべきことを確実に引き継ぎ、高い使命感をもって岩手の復興・発展を支える子どもの育成を進めていかなければならない。
このような状況を踏まえ、私たち校長は、「岩手県教育振興計画」の基本目標である「学びと絆で 夢と未来を拓き 社会を創造する人づくり ~自分らしい生き方の実現にむけた 新たな時代のいわての教育」の実現に向け、確かなリーダーシップの下、学校組織の活性化を図り、創意に満ちた特色ある学校経営を推進する必要がある。また、直面する教育課題に迅速かつ適切に対応し、教職員一人一人が各自の力を存分に発揮できる職場づくりを進めるとともに、魅力ある学校づくりを一層推進することが求められている。さらに、令和7年度は、次期学習指導要領についての本格的な検討が始まる大切な時期であり、現行指導要領の着実な実施とともに、新しい教育過程の編成に向け自ら高い問題意識をもち国の動向を注視していく必要がある。
岩手県小学校長会は、こうした現状を深く認識し、「明日を拓く岩手の絆」を会員の総意としながら、本県学校教育の現状と課題の把握に努め、東日本大震災やコロナ禍等における学校経営を通して学んだ校長の決断の重さを忘れることなく、校長自らの使命を自覚し、教育的識見を高め合う必要がある。
また全国連合小学校長会や東北連合小学校長会と効果的に連携しながら、教育活動の一層の充実と向上のため、学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止め、校長としてのリーダーシップを存分に発揮し、家庭や地域の信託に応えていかなければならない。
そのため、今年度の本会の活動方針を以下のとおり定める。
1 創意に満ちた特色ある学校経営の充実
国や県の教育改革の動向や新学習指導要領の趣旨、復興教育の方向性を的確に把握し、家庭や地域との連携・協働を推進する。確かな経営理念のもと、社会に開かれた教育課程の編成と着実な実施、評価、改善を行い、「生きる力」を育み、より一層創意に満ちた学校経営の充実に努める。
2 教育の復興に向けた支援の継続
東日本大震災対策特別委員会の設置を継続し、被災地区の学校運営上の諸課題や本県全体の復興教育の現状を把握するとともに、課題の改善に向けた発信や取組を行い、復興教育の充実を図る。また震災地訪問を実施し被災地の情報を共有することで、震災の教訓を未来に継承する活動の充実を図る。
3 専門職としての識見、力量の向上と教職員の人材育成の推進
校長自らが主体的に学び続け、高い同僚性と多様な専門性を有する教職員集団の形成を目指し、主題研究や調査活動等に取り組み、校長としての識見や指導性を高めるための研鑽に励む。また、教職員一人一人の経験、職責等のニーズに応じた研修内容等について、対話や研修履歴の活用を通じた助言、指導を行うことで、教職員の人材育成と専門性の向上に資する取組を推進する。
4 互いの人権や多様性を認め合う教育の推進
いじめや不登校の問題や情報モラル等への適切な対応に向け、生命の尊重や他人を思いやる心、多様性を認め合う心、生活上の規範に基づいて判断し行動しようとする心等、人権意識や規範意識を高める教育の充実を図る。また、組織的な支援体制を構築し、すべての子どもたちにとって安全で安心な学校づくりを推進する。
5 特別な支援を要する子どもの支援体制の充実に向けた教育の推進
障がいのある子どもの自立を促し、社会の一員としてよりよく生きるための資質・能力の育成に向け、一人一人の教育的ニーズを把握しながら、適切な指導や支援の充実を図る。また、特別支援学級の学級編成基準の改善や教育環境の整備、教職員の専門性を高める研修等、支援体制の拡充を図る取組を推進する。さらに、関係機関との連携体制の整備を進め、特別な支援を要する子どもの多様な学びの場の充実に努める。
6 学校のウェルビーイングの向上に向けた働き方改革の推進
教職員一人一人の日々の生活や教職員人生を豊かにすることが、よりよい教育活動に資するものであるという学校における働き方改革の趣旨を踏まえ、課題意識をもって現状を把握し、課題の共有及び解決に努める。また、教職員の健康面での安心感や業務への充実感等の向上に向け、情報交換の機会の充実を図るとともに、地域社会や関係諸機関、関係諸団体と連携した環境改善等の取組を推進し、学校のウェルビーイングの向上を目指す。
7 教育諸条件の改善に向けた取組の促進 GIGAスクール構想におけるICT環境や人的配置を含めた教育環境の状況、感染症への対応等、教育課題に関わる情報の共有に努めながら、質の高い教育と安定した学校生活を子どもたちに保障する。そのために、情報収集や調査研究活動及び要望活動を実施し、関係諸機関、諸団体と連携しながら人的措置の充実や環境整備等、教育諸条件の改善・整備への取組を促進する。
8 会員相互の連携強化と広報活動の充実 地区校長会との連携を密にするとともに、各地区の教育実践や復興教育、現状と課題等に関する情報交流などを推進しながら、会員相互の連携強化に努める。また、全国連合小学校長会、東北連合小学校長会との連携を重視し、研究大会・調査活動等に積極的に参加・協力する。さらに、様々な情報や調査の結果等について、適宜効果的に周知することで広報活動の一層の充実を図る。